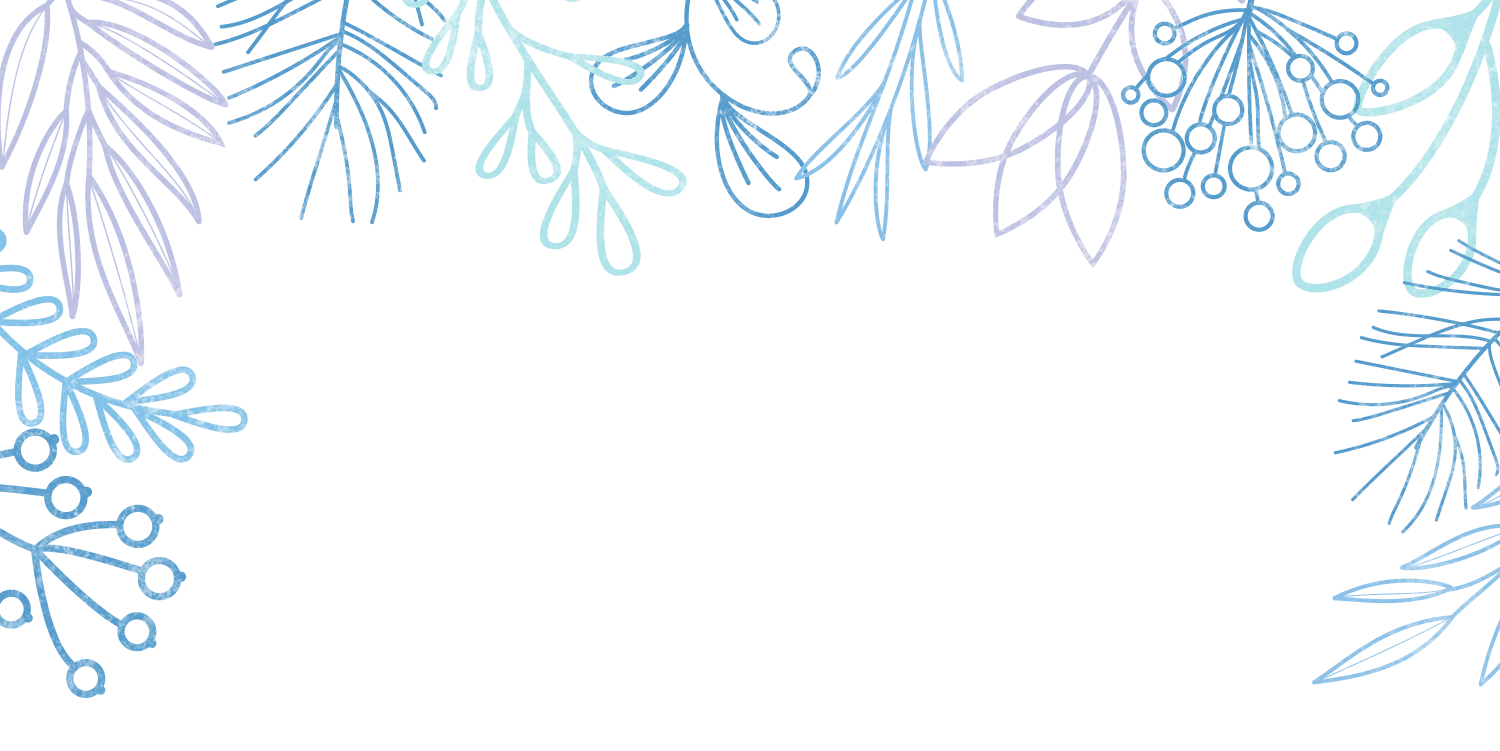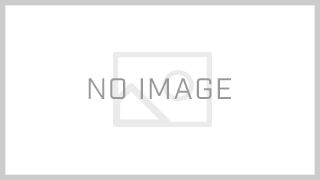【医療費控除&セルフメディケーション】サラリーマンも確定申告すればお金が戻ってくる?!
いよいよ確定申告が始まりましたね。
会社員の方は「会社が年末調整してくれているから自分は関係ない~」と思っていませんか?
たしかに扶養控除や社会保険料控除などは会社に書類を出すだけで行なってもらえます。しかし、自分で確定申告を行わないと受けられない控除もあるのです!
そのうちの1つに、「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」があります。これらは入院や治療のためにかかった費用の一部が還付される仕組みで、上手に活用することで税負担を軽減できます。
今回の記事では、それぞれの内容、対象となる人・治療、利用するにあたっての注意点を詳しく解説していきます。
ぜひ参考にしていただいて、必ず確定申告を行いましょう!
1.控除とは
「そもそも控除って何?」と思っている方のために簡単に解説します。
まず、税金は以下の計算式で算出されます。
給与ー控除=課税所得
算出された課税所得に税率がかけられて税金が発生します。
もうこれで控除の重要性が分かった人もいるのではないでしょうか。
控除は税金として取られる金額を少なくしてくれる私たちの味方です!
給与が同じであっても控除を増やすことで課税所得が下がるため、その分税金が安くなります。これがいわゆる節税というものです。
給与が300万円のAさん(控除50万円)、Bさん(控除100万円)の場合で比較してみましょう。
Aさん 給与300万ー控除50万=課税所得250万円
Bさん 給与300万ー控除100万=課税所得200万円
2. 医療費控除とは
医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、その超過分の医療費を控除することができます。日常的に病院に通っている方や妊娠・出産、レーシックなどで年間10万円以上支払った方が使うことができます。
また、配偶者や親族の医療費も合わせて申告することができます!
そう考えたら、意外と10万円くらいは支払っているのではないでしょうか?
2-1. 医療費控除の対象となる費用
具体的には以下の費用が該当します。
- 病院・診療所での治療費(診察料、手術費、入院費)
- 薬代(処方薬、薬局で購入した薬)
- 予防接種費用
- 治療に必要な検査費用
- 歯科治療費(金歯、インプラントなど)
- 義肢や義眼、補聴器などの購入費用
- 治療のための通院にかかる交通費(公共交通機関を利用した場合)
- 視力矯正のための眼鏡代(医師の処方がある場合)
2-2. 医療費控除の対象外となる費用
以下の費用は医療費控除の対象外となります。
- 美容整形手術費用(医療目的でない場合)
- 健康食品やサプリメント代
2-3. 医療費控除の計算方法
医療費控除は、年間に実際支払った医療費の総額から保険金や給付金を差し引いた額が対象となります。以下の計算式で求められます。
- 控除額 = (窓口で支払った医療費 ー 保険金などで補填される金額)ー {10万円(所得の合計額が200万円未満の方は所得金額の5%)}
※控除額は最高200万円までです。
たとえば、1年間に支払った医療費が20万円で、保険金として5万円受け取った場合、実際に支払った医療費は15万円となります。この場合、15万円から10万円を引いた控除額は5万円となります。
窓口等で支払った金額20万円ー補填金額5万円ー10万円=控除額5万円
2-4. 医療費控除を受けるための注意点
- セルフメディケーション税制との併用はできません!
- 医療費を支払った領収書や明細書を必ず保管しておく必要があります(5年以上保管が必要)
- 控除額が10万円以下であれば、申告しても税金の還付はない場合があります。
3. セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制は、12,000円を超える対象医薬品を購入した場合に、税制上の優遇措置を受けられる制度です。
3-1. セルフメディケーション税制の対象となる費用
セルフメディケーション税制で控除できるのは、薬局やドラッグストアで購入した医薬品の費用です。ただし、以下の要件を満たすことが条件となります。
- 薬局やドラッグストアで購入した医薬品が、厚生労働省の「セルフメディケーション税制対象薬品」に該当すること(セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について)
- 医薬品を購入した年に、健康診断や予防接種を受けていること(特定健康診査、予防接種、がん検診、インフルエンザ予防接種など)
3-2. セルフメディケーション税制の対象薬品
対象となるOTC医薬品には、解熱剤、鎮痛剤、風邪薬、胃腸薬、ビタミン剤、サプリメントなどが含まれます。特定の効能・効果が記載されている薬が対象となるため、購入時にパッケージや説明書で確認することが重要です。
↓このマークが目印です
 国税庁「セルフメディケーション税制とは」引用
国税庁「セルフメディケーション税制とは」引用3-3. セルフメディケーション税制の控除額
セルフメディケーション税制では、年間で支払った医薬品の費用が12,000円を超える部分について、最大で88,000円までの控除を受けることができます。
以下の計算式で求められます。
- 控除額(最大88,000円) = 実際に支払ったOTC医薬品の費用 ー12,000円
たとえば、年間で50,000円分のOTC医薬品を購入した場合、12,000円を差し引いた3万8,000円が控除対象額となります。
年間に支払った金額50,000円ー12,000円=控除額38,000円
3-4. セルフメディケーション税制の対象者
セルフメディケーション税制を利用するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 健康診断を受けていること(企業の健康診断、人間ドックなど)
- 予防接種を受けていること(インフルエンザ、定期予防接種など)
3-5. セルフメディケーション税制を受けるための注意点
- 医療費控除との併用はできません!
- 市販薬のレシートや領収書は必ず保管しておきましょう(5年間保管)
- 健康診断や予防接種の証明書が必要になる場合があります。
- 控除対象となる薬の種類を確認し、申告時に適用される薬を選ぶ必要があります。 セルフメディケーションマークが目印です!
3. まとめ
医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらも確定申告を通じて節税、還付を受けることができる控除、制度となっています。
医療費控除は、実際に支払った医療費が10万円を超えると適用されるものであり、セルフメディケーション税制は12,000円を超える対象医薬品を購入した際に使える税制上の優遇措置です。
しかし、どちらか片方しか利用することができないため、自分にとってどちらの制度が有利かを各自で計算して選ぶ必要があります。
損をすることはないので必ず確定申告しましょう!
確定申告をしてお小遣い(還付金)をもらいましょう!
当サイトをご覧いただき、ありがとうございます。
当サイトでは「「こんな情報が欲しかった!」と思っていただけるような生活に役立つ知識やおすすめアイテムを筆者の体験談を交えて紹介しています😊
みなさんが豊かな人生を歩んでいけるよう応援しています!